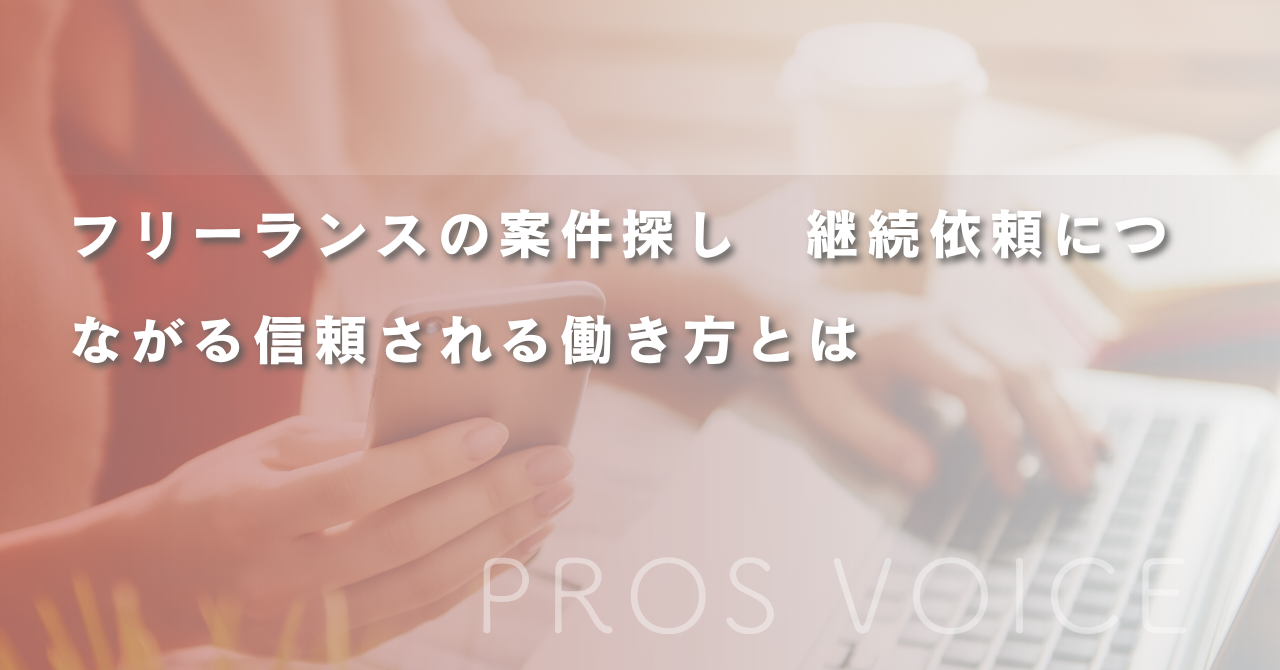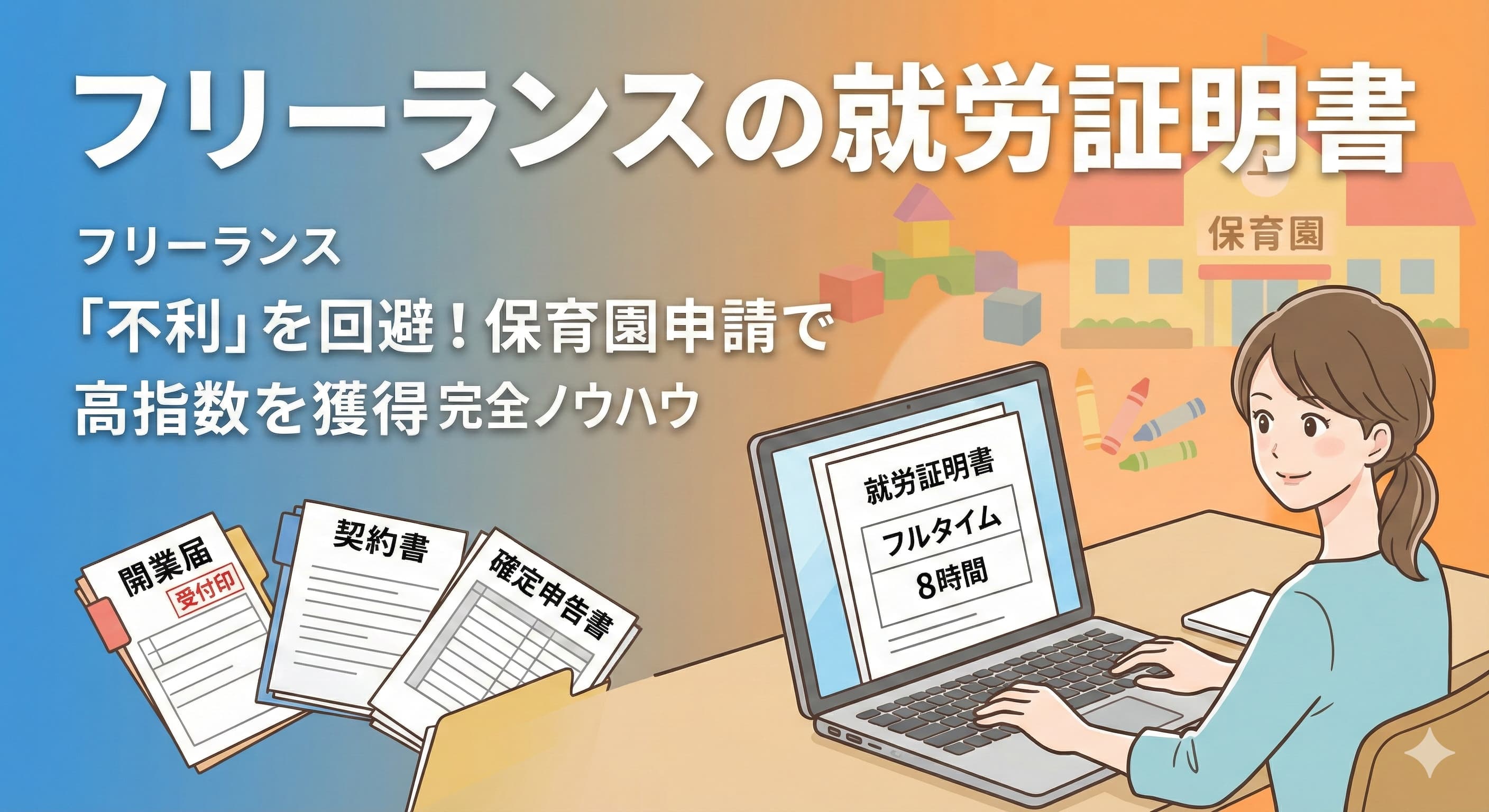【保存版】業務委託とフリーランスの違いとは?働き方・契約・メリットまで徹底解説
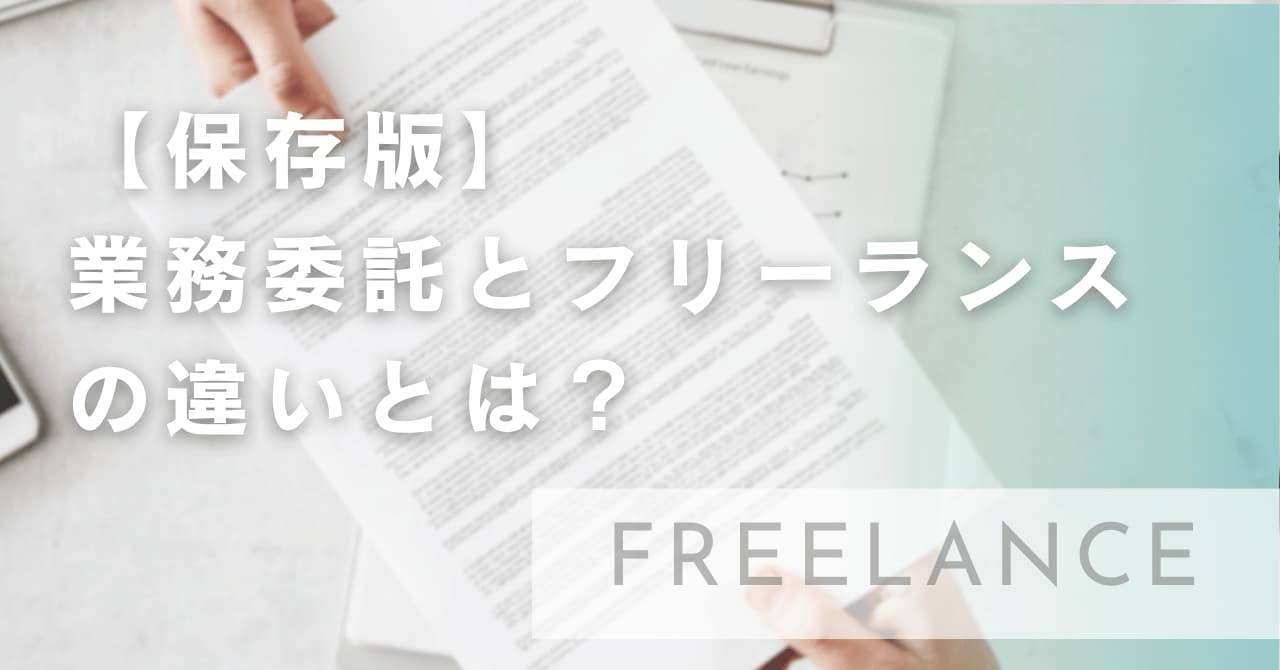
「業務委託」と「フリーランス」。
どちらも組織に縛られず働くイメージがありますが、この2つの言葉が指す意味は根本的に異なります。
近年、働き方改革やリモートワークの普及により、特定の企業に属さずに働く人が増えており、特にIT系(エンジニア、デザイナー)や文筆系(ライター、翻訳)などの専門職はフリーランスという働き方を選択する方も多くなってきています。
また、2024年11月1日にはフリーランスの立場を保護する「フリーランス保護新法(特定受託事業者法)」が施行されるなど、フリーランスを取り巻く法的な環境も整いつつあります。
この記事では業務委託とフリーランス、両者の定義と関係性、そして独立して働く上で必須となる契約や税務の知識、メリット・デメリットまで解説します。
業務委託とフリーランスの違い

業務委託とフリーランスという言葉はよく聞きますが、この二つの言葉は比較するカテゴリが違います。
フリーランス (Freelance):企業や組織に所属せず、独立して仕事を請け負う「働き方」や「人(個人事業主)」を指す言葉です。
業務委託 (Gyoumu Itaku):企業が外部の企業や個人(フリーランスを含む)に業務の一部を任せる際の「契約形態」を指す言葉です。
フリーランスは業務委託契約で働くことが多い

フリーランスは、発注元(クライアント)と業務委託契約を締結した上で業務を遂行することが多いため、二つの言葉が同じ意味として使われがちですが、イコールではありません。
つまり、「フリーランスという働き方をする人が、クライアントと業務委託という契約形態を結ぶ」というのが正しい関係性です。
また、フリーランスによく似た言葉として「個人事業主」がありますが、これは税務上の区分であり、フリーランスの多くは個人事業主として開業届を出しています。
業務委託と雇用契約の違い

これからフリーランスを目指す方は、会社員(雇用契約)と業務委託契約の違いを理解する必要があります。
| 比較項目 | 雇用契約(会社員) | 業務委託契約(フリーランスなど) |
| 法的立場 | 労働者と使用者(雇用主) | 対等な事業者同士(発注者と受託者) |
| 指揮命令権 | あり:企業が業務内容、場所、時間を指示できる | なし:受託者側(フリーランス)が裁量権を持つ |
| 労働法適用 | 適用される(労働基準法など) | 適用されない |
| 社会保険・年金 | 企業と折半(健康保険、厚生年金) | 全額自己負担(国民健康保険、国民年金) |
| 税金処理 | 企業が源泉徴収、年末調整を実施 | 原則、自己で確定申告が必要 |
| 報酬の対象 | 労働力(時間・勤務)に対して給与 | 成果物または業務遂行そのものに対して報酬 |
業務委託契約では、働く場所や時間は受託者側が自由に設定できますが、その代わりに労働基準法などの保護は受けられず、最低賃金の保証や有給休暇、休業補償などもありません。
フリーランスが会社員のように管理される偽装請負とは?

業務委託契約であるにもかかわらず、実態としては雇用契約と変わらず、企業がフリーランスに対し細かく業務遂行の方法や勤務時間を指示・管理している状態を「偽装請負」といいます。
企業側が社会保険料の負担を避けたい、または解雇規定がないため人員調整を容易にしたいといった理由で偽装請負を行うケースがありますが、これは労働基準法などの違反にあたる違法行為です。フリーランス側にはメリットがないため、指揮命令を受けていると感じた場合は毅然と対応する必要があります。
業務委託契約の種類(請負契約・準委任契約)を理解する

「業務委託契約」は法律用語ではなく、実務上の通称です。民法上、業務委託は主に以下の3つの契約形態に分類されます。
請負契約
特定の成果物(完成品)の完成・納品を目的とする契約です。
記事執筆・納品、ウェブサイト制作、システム開発(完成)、製造委託。
委任契約
法律行為の遂行を目的とする契約です。
弁護士による訴訟代理や法律相談、税理士による税務相談。
準委任契約
法律行為以外の業務の遂行を目的とする契約です。
コンサルティング、システム運営やサポート、秘書業務、研修講師。IT業界でいうSES(システムエンジニアリングサービス)契約は、業務委託の中の準委任契約に該当します。
フリーランスとして業務委託契約で働くメリット・デメリット

フリーランスとして業務委託契約で働くことには、会社員にはない大きな魅力と、自己責任に基づくリスクの両方があります。
メリット:自由と高収入の可能性
働き方の自由度が高い
雇用契約と違い、基本的に勤務場所や時間に縛られません。自分のライフスタイルやペースに合わせて仕事量を調整できるため、育児や介護との両立もしやすいことが特徴です。
得意分野の業務に専念できる
苦手な仕事や意に沿わない仕事を断り、自分のスキルや経験を最大限に活かせる案件を選んで働けます。専門分野に特化することで、仕事へのモチベーション維持やキャリアの専門性深化につながります。
成果次第で高収入が目指せる
特に請負契約では成果物に対して報酬が支払われるため、スキルアップや努力次第で報酬の上限なく高収入を目指すことが可能です。また、複数のクライアントと契約を結び、同時に報酬を得ることで収入源を分散できます。
人間関係のストレスが少ない
業務委託契約では、依頼者と受託者は対等な関係であり、会社員のような日常的な上下関係や派閥争いといったストレス要因から解放されるメリットがあります。
デメリット:不安定さと自己責任
収入が不安定になりやすい
業務委託は案件ごとの契約であるため、仕事が途切れる可能性があり、会社員のように毎月安定した収入が保証されるわけではありません。クライアントの経営状況の変化などで急に契約が打ち切られるリスクもあります。
事務作業(税金・保険など)をすべて自分で行う必要がある
会社員であれば会社が行う確定申告、経費処理、請求書発行、国民健康保険や国民年金などの手続きや納付をすべて自分で行う必要があります。
労働基準法の対象外となる
労働者ではないため、労働基準法が適用されず、最低賃金や労働時間の制限といった保証がありません。働き方によっては時給換算で最低賃金を下回る可能性もあるため、自己管理が必須です。
社会的信用度が低下する可能性がある
収入の安定性から、会社員と比べて住宅ローンやクレジットカードなどの金融関連の審査が通りにくいと言われることがあります。
他のフリーランスのメリット・デメリットは、下記の記事で解説しています。

発注側(企業)にとっての業務委託契約のメリット・デメリット

企業がフリーランスに業務委託を活用することは、リソース戦略において多くの利点をもたらしますが、同時に注意すべき法的リスクも存在します。
メリット:リソース効率化と専門性の確保
専門性の高い即戦力人材を確保できる
フリーランスには専門性の高いハイスキル人材が多く、自社で教育や研修をしなくても、特定のジャンルに関する即戦力となる知識やノウハウをすぐに活用できます。
コスト効率が良い(変動費化)
フリーランスを活用する場合、報酬以外の採用コストや社会保険料の企業負担が発生しません。必要な時に必要な分だけリソースを確保でき、固定費を変動費に変換できるため、経営の安定性や効率化につながります。
コア業務にリソースを集中できる
ノンコア業務(直接利益につながらない業務)を外部に委託することで、社内リソースを企業の成長に直結する重要な活動(コア業務)に集中させることができます。
スピード感を重視できる
フリーランスへの依頼は、企業間委託と比べて事務処理や承認手続きをカットできることがあり、迅速な発注から納品を期待できます。
デメリット:リスクと管理の難しさ
指揮命令ができない
業務委託では受託者(フリーランス)に対して直接的な指示や、勤務場所・時間の拘束が禁止されています。そのため、業務の進捗や品質を会社員のように細かく管理することが難しくなります。
ノウハウが蓄積されにくい
難易度の高い業務や専門的な業務を外部に切り出すと、社内での知識移転やノウハウ蓄積が遅れ、将来的に自社内で対応できなくなるリスクがあります。
継続的な依頼ができる保証がない
優秀なフリーランスは他の企業からも声がかかる可能性が高く、病気や個人の事情などにより、突然稼働ができなくなるリスクもあります。
情報漏洩のリスクが高まる
社外の個人に業務情報やデータを提供する必要があるため、自社の管轄外での情報漏洩やセキュリティリスクが高まります。
フリーランスと業務委託契約を結ぶときの注意点

トラブルを避け、安心して業務を遂行するために、フリーランス側も発注側(企業)側も、契約時に以下の点を厳しくチェックすることが不可欠です。
契約内容を書面で明確にする
口頭での合意だけでは、後々認識のずれやトラブルに発展するリスクが高いため、必ず報酬や業務内容が明記された業務委託契約書を締結し、保管しておくことが重要です。
業務の範囲と内容
どこからどこまでが業務の範囲なのかを具体的に明記し、曖昧な表現(例:「関連業務を含む」、「システム開発業務全般」など)を避けて、双方の認識のズレを防ぎます。
報酬と支払い条件
報酬額、支払い日、支払い方法(定期払いか成功報酬か)、振込手数料の負担、検収基準などを明確に記載します。
経費の扱い
交通費や備品代などの必要経費が報酬とは別に支払われるのか、誰が負担するのかを契約締結前に確認し、明確に記載します。
知的財産権・著作権の所在を明確にする
デザインやコンテンツなど、著作物が発生する業務の場合、著作権や知的財産権が発注者と受託者(フリーランス)のどちらに帰属するかを契約書に明記してください。
フリーランスにとっては、納品した成果物を自身のポートフォリオとして公開できるかどうか(著作権が発注者に譲渡されると公開できないことが多い)に関わるため、事前に確認・交渉が必須です。
契約解除や修正対応のルールを確認する
契約解除・途中解約
契約期間、中途解約の条件、通知期間などを明確にしておきましょう。一方的な解除や不利益変更はトラブルの元となります。
修正対応の範囲
成果物の修正回数の制限、追加修正費用が発生する条件などを明確にしておかないと、認識の違いからトラブルに発展する可能性があります。
法的リスク(偽装請負)の回避
発注者側がフリーランスに対して指揮命令や勤怠管理を行うと「偽装請負」とみなされるリスクがあります。業務委託契約を結んでいても、実態が雇用と同様と判断されると、発注者側には各種保険料の支払いや有給付与の義務が生じる可能性があるため、注意が必要です。
また、2024年11月1日に施行されたフリーランス保護新法では、取引条件や支払い方法の明示、禁止行為の明確化、ハラスメント禁止などが義務化されており、フリーランスを活用する企業は法律の適用範囲とルールを理解しておく必要があります。
よくある質問

Q1: 個人事業主とフリーランスは同じですか?
A: 個人事業主は税務上の区分を指します。税務署に開業届を提出し、法人を設立せずに事業を行っている個人のことです。
一方、フリーランスは特定の組織に属さずに働く働き方・スタイルを指します。フリーランスとして働く人の多くは、税務上のメリットを得るために個人事業主として開業届を提出しています。
Q2: フリーランスとして業務委託案件を獲得する方法は?
A: 主な案件獲得方法は以下の通りです。
フリーランスエージェントの活用:スキルや希望に合った案件を紹介してくれ、交渉や契約処理を代行してくれるため、業務に集中しやすく、初心者にもおすすめです。
クラウドソーシング:インターネット上で案件を探し、応募できます。案件数が多く、実績を積むのに適しています。
SNSや直接営業:自分のスキルやポートフォリオをSNSで発信したり、知人からの紹介や企業へ直接アプローチしたりして案件を獲得します。
他にも、案件探しや継続依頼に関して
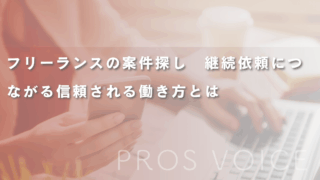
Q3: 「業務委託フリーランス」と求人に書いてあるのはどういう意味ですか?
A: これは「フリーランスという働き方をする方を、業務委託契約で募集している」という意味です。フリーランスという言葉は「働き方」を意味しますが、求人や募集においては「業務委託契約を結ぶ独立した個人」を指す慣習的な表現として使われています。
フリーランス=働き方、業務委託=契約形態
「フリーランス」は、組織に依存せず個人で独立して働く働き方や人を指し、「業務委託」は、その働き方を実現するための契約形態(請負、委任、準委任)を指します。
フリーランスとして成功するためには、自由な働き方や高収入の可能性というメリットを享受する一方で、収入の不安定さや社会保障の自己責任といったデメリット、そして契約内容の重要性を正しく理解することが第一歩です。
契約を結ぶ際は、業務内容、報酬、経費、著作権、そして法的リスク(偽装請負)について、口頭ではなく書面(業務委託契約書)で明確にしておくことが、自分自身の権利と安定したキャリアを守るための鍵となります。